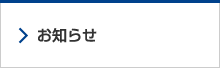お知らせ
令和7年度 第1回発酵・微生物及び酵素利用研究会を開催しました
令和7年7月14日(月)、東京農業大学オホーツクキャンパスにて、今年度1回目の発酵・微生物および酵素利用研究会が開催されました。
今回は、食品の品質評価に関する最新の研究や地域資源の活用事例について、2名の講師よりご講演をいただきました。
はじめに、北見工業大学 准教授のFENG CHAO HUI(フォン・チャオ・フイ)氏より、食品中のATPを非破壊で測定する技術として、「ルミネッセンス法」と「ハイパースペクトルイメージング」の併用による応用事例が紹介されました。この手法は、食品の微生物検査や品質変化の検出など、現場での幅広い活用が期待されています。
続いて、一般社団法人もち麦フィールズ 代表理事の今井 貴祐氏より、オホーツク地域で栽培されたもち麦品種「富系1103」についての紹介がありました。β-グルカン含量が高く、収量にも優れるこの品種を用いて開発された「もち麦味噌」の取り組みについて、開発の背景や特徴を含めて解説されました。
参加者は11名と少人数ながらも、各講演後には活発な質疑応答が行われ、参加者同士の意見交換も見られるなど、有意義な研究会となりました。
・1演題目
「ルミネッセンス法とハイパースペクトルイメージングを併用した迅速かつ可視化可能な微生物検査手法」
北見工業大学 准教授 FENG CHAO FUI(フォン・チャオ・フイ)氏


・2演題目
「富系1103の利用拡大 ~麹・味噌になるまで~」
一般社団法人もち麦フィールズ 代表理事 今井 貴祐 氏